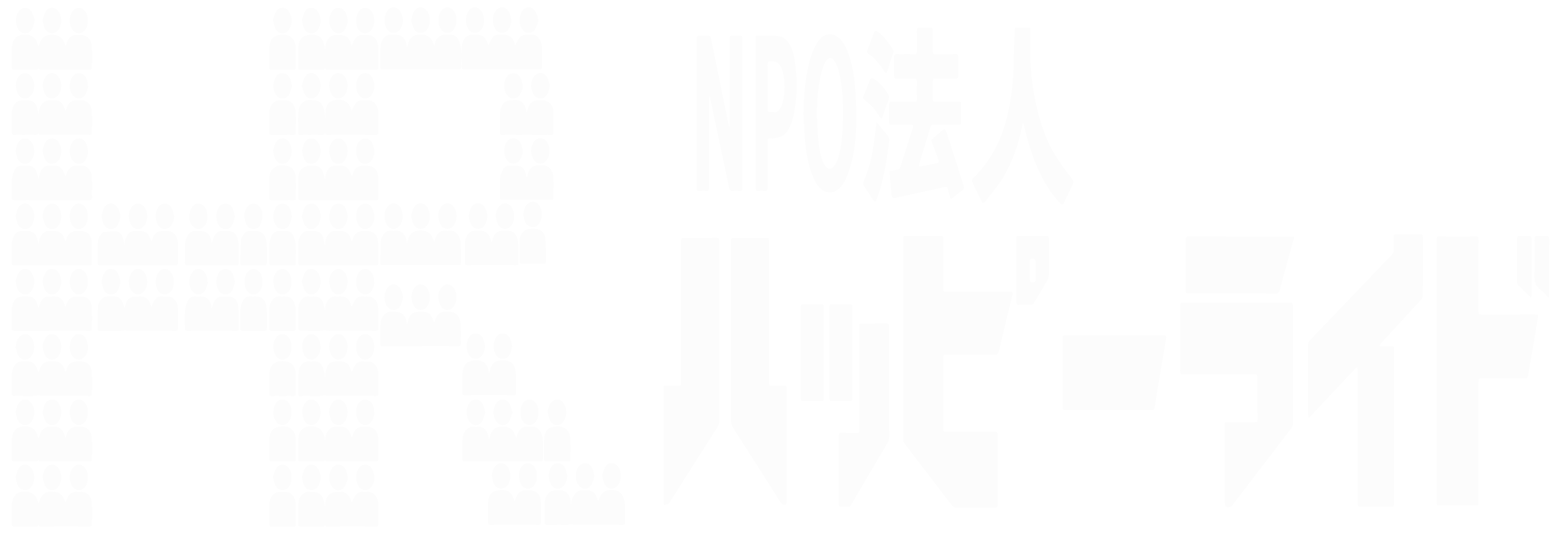原点は東日本大震災での現地体験。
この取り組みの起点は、2011年の東日本大震災に遡る。
現地で昼は流木や泥の撤去作業、夕方からは福祉関係者、施設、社協への聞き取りを行い
以下の事を確認して何とも言えない気持ちになった
災害関連死
多くの障がい者が避難所にいる事が出来ず、津波で助かったにもかかわらず命を落とした事実
不都合な避難所の真実
障がい児のお母様が「私たちが謝っていれば丸く収まるんです」と当たり前のように話されたこと。
支援が届かない状況に直面し、制度の隙間に多くの人が取り残されている現実を目の当たりにした。
【新聞でも紹介されました】
ネクトバトン方式で共感型ムーブメントを巻き起こす
そこで考えたのが 共感×巻き込む×つながり
このような状況を根本的に改善するには、「支援を受ける側」と「支援する側」という関係性を超えた、顔の見える関係性の構築が不可欠であると考えた。
そして、福祉・防災に興味を持って貰う事を目的として
“参加型エンタメ”という手法で地域社会に広げる4つのSTEPで絆を創る
「絆創航プロジエクト」を展開しはじめた。
「気づく」から「関わる」へ。みんなで考える防災のカタチ
災害時、即時に避難できる人は限られている
視覚障がい者やその家族、車いす利用者、高齢者、発達障がいのあるいわゆる「災害時要配慮者」の多くが、避難をあきらめざるを得ない状況に置かれている。
これは個人の責任や判断力の問題ではなく、社会構造上の課題である。
具体的には以下のような障壁が存在している
-
避難所に関する情報が視覚・聴覚に配慮されていない(点字・音声・やさしい日本語等の不足)
-
移動手段が確保されていない(公共交通や送迎体制の不備)
-
受け入れ態勢が未整備(福祉避難所の存在や運用が周知されていない)
これらの要因が、物理的・制度的・情報的な災害時の「避難の選択肢」を狭めている。
主な受益者と波及効果
本事業の主な受益者は、視覚障がい者、車いすユーザー、発達障がい者、要介護高齢者といった「避難の困難性を抱える当事者」およびその家族である。加えて、本来この課題に当事者性を持たない地域住民もまた、重要な対象と位置づけている。
イベントやワークショップへの参加を通じて、普段は見えにくい困難さに「気づく」ことが、住民の行動変容や地域連携の第一歩となる。
「かわいそう」ではなく共感ポイントを作り出す
展望:共感によって支え合う地域社会の実現
目指す社会像は、「災害時、共感にもとづいて支え合う地域社会」
「かわいそうだから助ける」という一方的な視点ではなく、
「困っている状況に気づいたから」「同じまちで暮らしているから」動くという“共感型ムーブメント”の
方が健全だと思っている。
そもそも支援が特別な行動ではなく、日常的な関わりの延長として根づくような地域。
そうした社会を実現するために、今後も「誰もが参加できる防災・共生の入口」として
体験型の取り組みを発展させていく。
そのために遊びの中の学びをどんどん取り入れていこうと考えたのが真っ暗フェスなんです
ばかばかしくてたまらない
暗闇エンターティメント「真っ暗フェス」
暗闇でエンターティメントは可能なのか?
2025年の最大の事業として安全面はどうか?参加したいと思えるコンテンツは何か?
そもそも面白いのか????を日夜真剣に考えています。