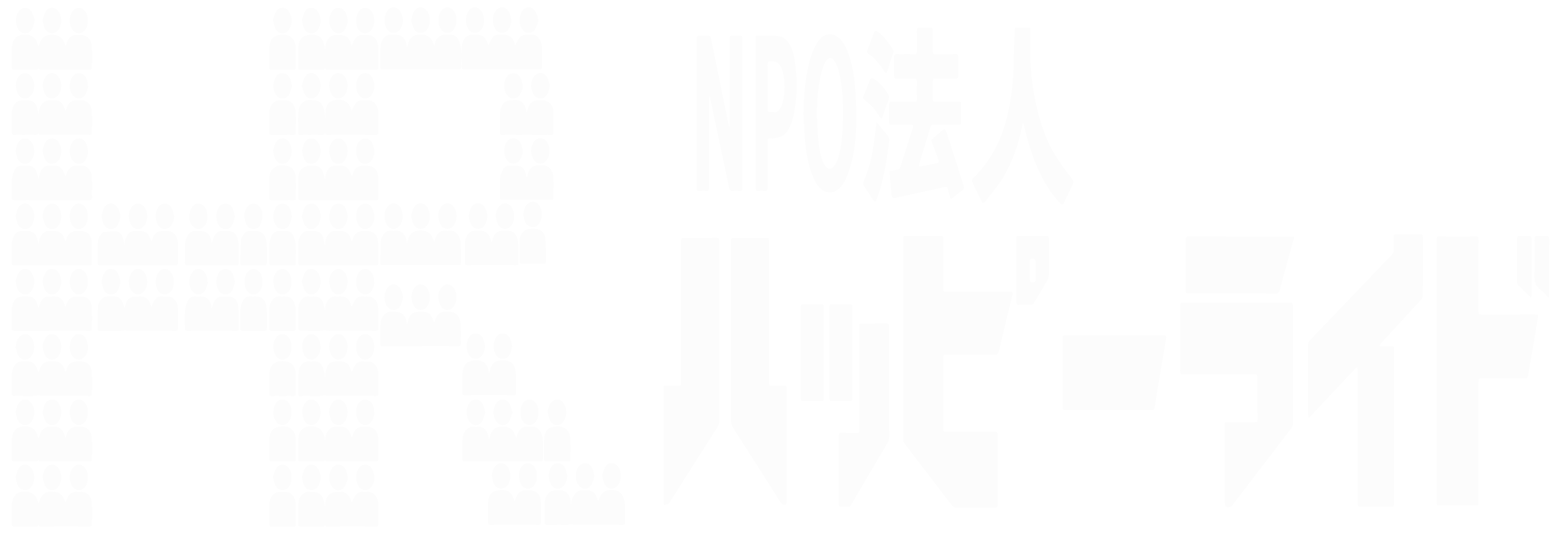「事前防災」距離でなく心で繋がる「なかま」の話|実施報告
11月8日、中間市で開催した「障害当事者と考える避難所づくり」の場に
ご参加いただいた皆さま本当にありがとうございました。
まず初めに――
お集まりくださった障害当事者ののみなさん。
社会福祉協議会の職員の皆さま。
自治協議会の会長、人権尊重協議会の皆さま。
お休みでありながら足を運んでくださった行政職員の皆さま。
そして、打ち合わせの段階から伴走してくださった「つばさの会」の皆さま。
この場を一緒につくってくださったことに、心から御礼申し上げます。
「できない」は、個人のせいじゃない。
今回の会で一番伝えたかったことは、とてもシンプルです。
「できないことがあるのは、その人がダメだからではない。」
避難所のルール、誘導の仕方、情報の届け方、スペースのつくり方。
それらが“その人仕様”になっていないから、結果として「できない」が生まれているだけだ
という事なんです。
さぁ出来なことを沢山体験してみよう

だからこそ、
「何ができないんだろう?」
「どこで困るんだろう?」
「その困りごとを解決するには、どんな仕組みや声かけが必要なんだろう?」
**みんなで事前に集めて考えることこそが“事前防災”であり、
“地域レジリエンス”**だと考えています。
今回、当事者の皆さんから出てきた「本当の困りごと」は
どれも現実的で、同時に“今なら変えられるもの”ばかりでした。
その声に、地域の人たちや行政職員が真正面から耳を傾け、
一緒に解決の糸口を探る姿があったことは、
この取り組みの何よりの成果だと思っています。
「断られた経験」から、「自分たちでつくる避難所」へ
印象的だったエピソードがあります。
「避難所に入りたいと伝えたのに、“もういっぱいだから”と断られたことがある。」
その言葉には、悔しさや不安だけでなく、
「自分たちは後回しにされるのではないか」
という深いあきらめがにじんでいました。
でも、この話をきっかけに空気が変わりました。
「それなら、私たち“つばさの会”としても、ちゃんと受け入れられる避難所の形を考えよう」
「視覚障がい者同士でつながれる仕組みがあった方がいい」
視覚障がい者のLINEグループを立ち上げることがその場で決まりました。
これは単なる連絡網ではなく、
「誰かが取り残されないようにするための、小さくて大きなセーフティネット」です。
“断られた経験”で終わらせず、
「だったら自分たちで仕組みをつくろう」という一歩に変わったことは、とても革新的な出来事でした。
この日、参加してくれた当事者の方々は、知らない人との共生体験に緊張もあったはずです。
それでも会場には、安心して笑い合い、冗談を交わしリラックスしてできるほど
楽しい空間になりました。
「ここは大丈夫だ」
「ここには、わかろうとしてくれる人がいる」
そう感じてもらえたとしたら、この取り組みは、
もうすでに“避難所づくり”の第一歩として成功しているのだと思います。
これからも、当事者の声をまんなかに置きながら、
“できない”を責めるのではなく、“できる環境”を一緒につくっていく地域でありたい。
そのスタートラインに立ってくださった皆さまに、改めて感謝します。