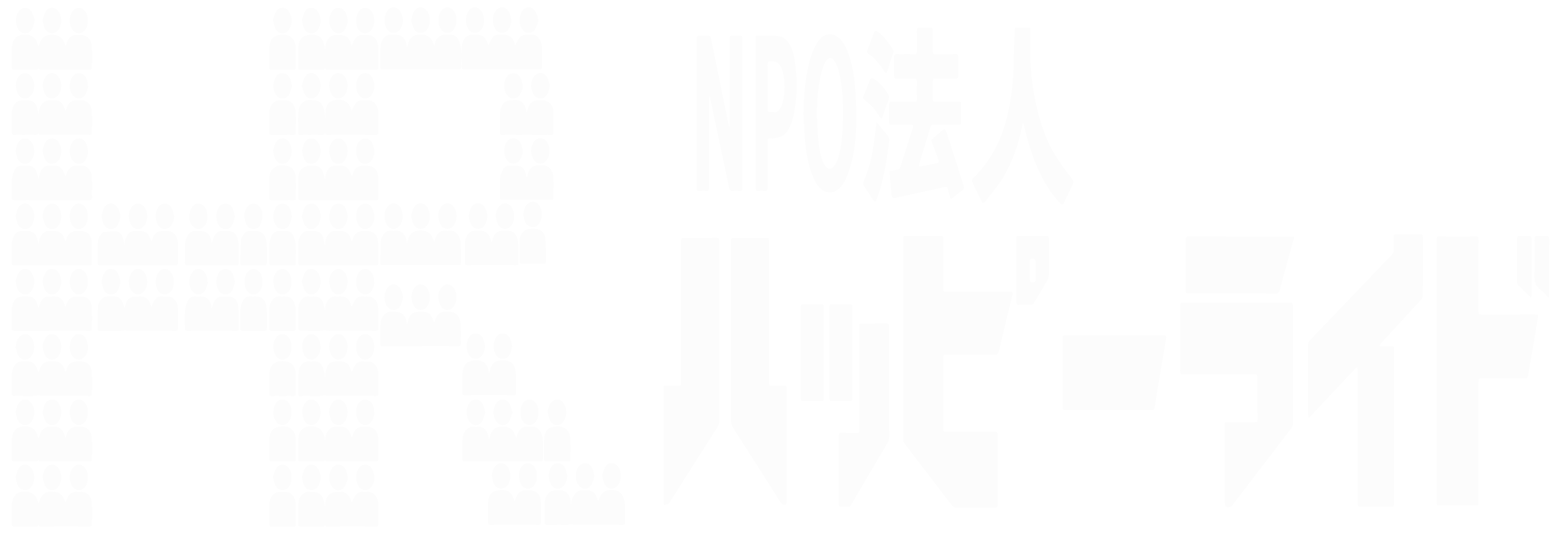見えないから芽生えた感情は、「かわいそう」が「信頼」に変わる
この言葉の中にハッピーライドの哲学である「共感→共助」のモデル、そして社会を変革する強い意志が凝縮されている。
良くも悪くも僕たちは、見えすぎる時代を生きている。
スマホを開けば膨大な情報が飛び込んできて、いつしかデータや数字、顔ぶれ、肩書きで世界を判断するようになった。
そしていつの間にか、目に見えるものだけが「正しい」と信じ込む。
そうして導き出された答えは、果たして本当に「正解」なのだろうか?
真の課題は、いつだって目に見えない場所にある。
とさえ思っている。
物理的な「見えない」が、心を解放する
分かって欲しいのはハッピーライドが創り出す「暗闇」は、ただの真っ暗な空間ではない。
それは、僕たちが目に見える情報に依存し、鈍ってしまった感覚をリセットするための場所だ。
そして、みんなの感度をあげるための仕掛けだと思っている。
視覚を奪われた参加者は、声、足音、息づかい、に気を配り、そして互いの存在だけを頼りに一歩を踏み出す。
この時、普段は誰も頼りにしない「感性」と「信頼」が研ぎ澄まされる。
情報過多な現代社会で失われがちな、最も原始的で、最も強力なコミュニケーションが、この場所で再構築される。
抽象的な「見えない」が、未来を拓く
この体験は、僕たちの日常の課題を象徴していて、
そして抽象的な見えないが数多く存在している事に気付く
防災福祉の正解が見えない
共生社会のゴールが「見えない」
正解への道筋が「見えない」
人間関係の抱える悩みが「見えない」
僕たちは、目に見える情報だけを頼りにすると、この「見えない」壁の前で立ち尽くしてしまう。
だけど、「暗闇」という物理的な制約を乗り越えた人の感度はいっきにあがり感覚と信頼を羅針盤に変える事が多い
子ども達も想像力が働き自分の言葉で一生懸命に伝えてくれる。
きっと、彼らは、データやグラフには決して現れない、人々の感情や潜在的なニーズといった「見えない」本質を掴んでいる
そして、その感性で、誰も想像しなかった、唯一無二の**「最適解」**を導き出す。
「見えない」から始まった冒険が、見える世界の答えを見つけるんだ。 これが僕たちの哲学であり、
僕たちが「真っ暗フェス」を企画する、揺るがない意義だ。
僕たちの揺るがない哲学
「見えない」から始まった冒険はいつしか見える世界の答えを見つける。
「暗闇」で培った感性をもって日常に戻り現実を歩く事で
車いすユーザーが通行できない小さな段差や、視覚障がい者が混乱する無機質な音の壁に気づく。
**「見る」だけでは気づけなかった課題を、「感じる」**ことで
発見し、本当の意味で誰もが住みやすい街の「最適解」を見つけることができる。
もしかしたら「多様性の共生」という言葉の意味の受け取り方も変わるかもしれない。
それは、単なるイベントではない。
沢山の人の「感度」をリセットし、社会の「見えない壁」を壊すための
最も効果的なソリューションだ。