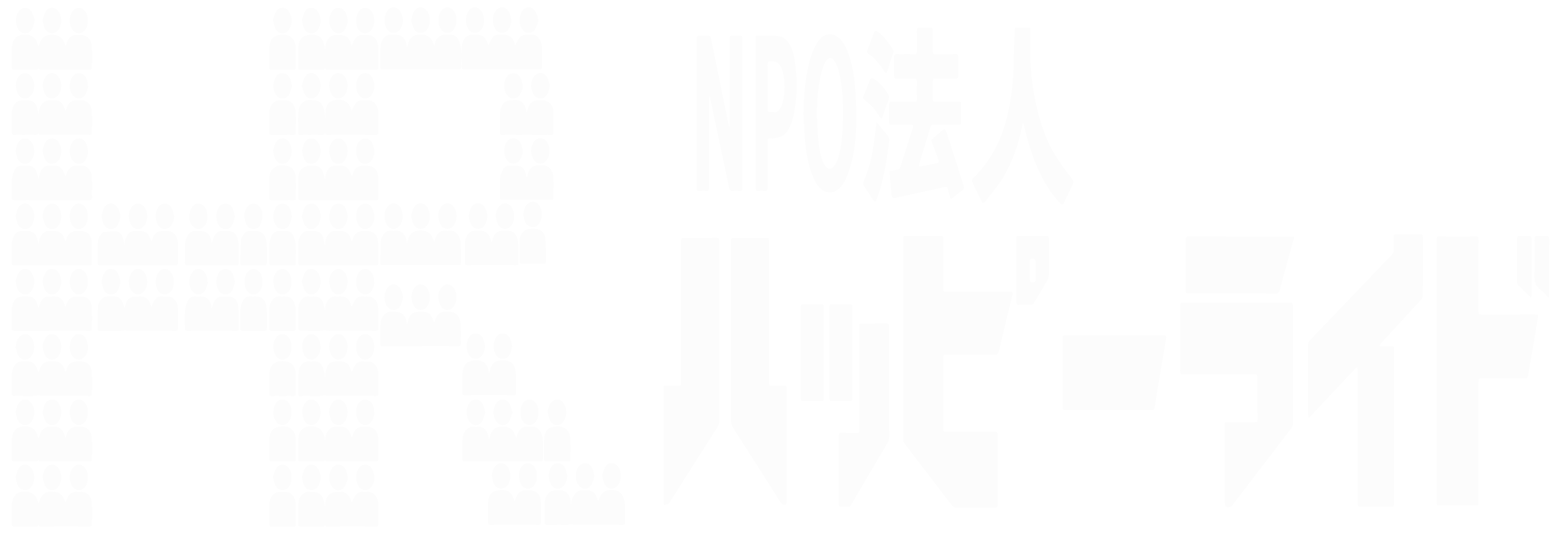ピボットした理由
トーマス・エジソンは多くの発明の裏で数々の失敗を経験し、特に電球の発明には約1万回の試行錯誤があったと語られています。彼は失敗を「うまくいかない方法を発見したこと」と捉え、決して失望せず、成功への過程と見なすことで努力を続けました。僕等も見習い即判断!!きりかえました。
僕達が進めている「地域のご近助ネットワークづくり」プロジェクト。
その柱の一つとして、当初計画していた防災フォーラムを、より参加型の
「暗闇体験型ワークショップ」へと大胆に変更しました。
この決断は、一見すると大きな方向転換に見えるかもしれません。
しかし、これこそがプロジェクトの成功に不可欠な「ピボット(方向転換)」だと確信しています。
今回は、なぜこの変更に至ったのか、そしてその先にどんな未来を見ているのかをお話ししたいと思います。
結論:フォーラムをやめた理由
フォーラム形式では、参加者が「防災」を他人事として捉えてしまいがちでした。登壇者の話を聞くだけでは、災害時に避難を諦めざるを得ない方々の存在を**「知識」**として知るに留まり、深い共感や行動へとつながりにくい。私たちは、頭で理解するだけでなく、心と体で感じてもらうことが必要だと結論付けました。
「体験」を重視するに至った経緯
参加型のワークショップへと舵を切ったのは、従来のやり方では目標達成が難しいと判断したからです。多くの人、特に親子世代を巻き込むためには、受け身の座学ではなく、楽しみながら能動的に参加できる仕掛けが不可欠でした。
そこで僕達は、子どもたちに人気の「読み聞かせ」や「演劇」という手法に注目しました。
五感を使い、物語の世界に没入する体験こそが、参加者の心に深く響くと考えたのです。
しかも・・それに暗闇体験をプラスするのです
参考にした成功事例:アンパンマンに学ぶ

この発想は、あの国民的ヒーロー、アンパンマンの誕生秘話からヒントを得ました。
このキャラは・・??www
やなせたかし先生が最初に出版した絵本『あんぱん』の主人公は、現在のアンパンマンとは全く違う姿でした。顔も汚れており、子どもたちには不評で、「こんなのアンパンマンじゃない!」という批判が届いたそうです。しかし、先生は「正義は、傷つきながらも身を削って誰かを助けることだ」という信念を貫きました。
この「子どもに媚びない、本質を伝える」という姿勢こそが、やがて多くの共感を集め、
アンパンマンを不動の存在にしたのです。
アリとキリギリスが成功事例に続く・・のか?

ハッピーライドの活動も同じです。単に「災害は怖い」とか少し重い話で伝えるのではなく、変化球で当事者の方々の気持ちを「暗闇体験」や「演劇」という手法に落とし込むことで抽象度が上がり、まるで架空の出来事のように伝えることが出来ながらリアルにも感じてもらえる・・そう考えています。
リアルな避難所の話を舞台や絵本で聞いてみて知って体験してもらう。
最初は驚かれたり、戸惑われたりするかもしれません。
しかし、この「一見、回り道に見える体験」こそが、参加者の心に深く残り、
「困っている人を助けるって、こういうことなんだ」と腑に落ちる瞬間を生み出すと信じています。
用意していた予算をフォーラム会場費から「暗闇で使える紙芝居・読み聞かせ冊子の製作費」に
司会・ゲスト謝金を「舞台演出費」へと変更しました。これは単なる経費の調整ではなく、
「知識の伝達」から「感情の共有」への大胆な挑戦です。
アンパンマンが批判を乗り越えて国民的ヒーローになったように、ハッピーライドもこの新しいアプローチで、地域に欠かせない**「ご近助ネットワーク」**を築いていきます。
ぜひ、今後の活動にご期待ください。