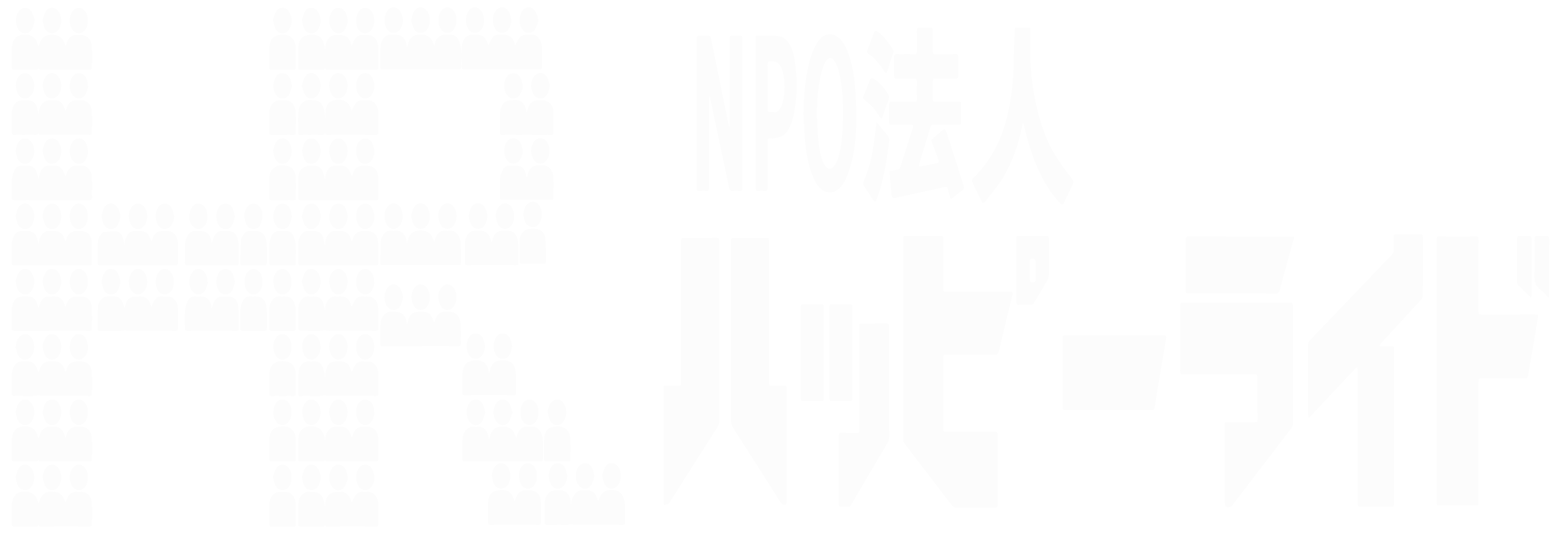「御近助ネットワーク」という言葉は、一見すると「御近所ネットワーク」と似ていますが、まったく異なる概念です。
御近所ネットワークは「向こう三軒両隣り」という言葉に象徴されるように、地理的な近さを基盤とした関係です。日常的に顔を合わせることはあっても、そこに必ずしも深い信頼関係や共通の目的があるわけではありません。
一方、御近助ネットワークは「同じ釜の飯を食った仲」「竹馬の友」「同じ障害をもつ人同士」「同じ趣味・志向を共有する仲間」といった、共通の体験や境遇をもとに築かれたつながりです。地理的な距離よりも「心の距離」が近い人たちが互いに支え合う新しい形のコミュニティなのです。
「御近所」と「御近助」の違いを整理する
「御近所」と「御近助」の違いを
- 御近所ネットワーク
- 基盤:地理的な近さ
- 特徴:日常のあいさつや地域行事を通じて顔見知りになる
- 限界:深い信頼関係や共通の目的がなく、非常時に助け合いが機能しにくい
- 御近助ネットワーク
- 基盤:共感・共通体験
- 特徴:同じ経験や価値観を共有しているため、信頼や支え合いが自然に生まれる
- 強み:災害時や困難な場面で「頼れる関係」として機能する
つまり、「御近所」は物理的な距離の近さ、「御近助」は心理的な距離の近さ。ここに本質的な違いがあります。
Cause(背景・課題認識)
近年、日本各地で自然災害が頻発し、「要支援者が避難をあきらめてしまう」現実が浮き彫りになってきました。従来の「御近所ネットワーク」は地理的な近さに基づく関係にすぎず、いざという時に互いを支えられる深い信頼や共感が必ずしも存在するわけではありません。また行政や福祉制度だけでは、すべての人を支えるには限界がある。こうした現実から、地域の中で新たな支え合いの仕組みが必要とされていました。
Occasion(きっかけ・発想の転換)
ハッピーライドは「暗闇フェス」などの体験型イベントを通じて、障がいの有無や立場を超えて人々が共感でつながる瞬間を数多く目の当たりにしてきました。同じ体験を共有した仲間は、単なる顔見知り以上の絆を築き、困難な時にも自然に支え合える。この実感こそが「御近助ネットワーク」という新しい概念を生み出すきっかけとなりました。
Target(目指す姿・目的)
ハッピーライドが目指すのは、血縁や地縁に縛られず、共感と共通体験を基盤とした支援関係を地域に根づかせることです。それは「かわいそうだから支援する」モデルではなく、「仲間だから一緒に支える」という新しい支援のかたち。御近助ネットワークは、災害時には実効性ある助け合いを、平常時には共生社会を育む土台となります。つまりこれは、時代が求める「支援者予備軍」を育てる仕組みであり、ハッピーライドの活動目的そのものなのです。
ハッピーライドが描く「御近助ネットワーク」の未来
NPO法人ハッピーライドが目指すのは、まさにこの「御近助ネットワーク」を地域に根づかせることです。
障がいの有無や世代を超えて、共通体験を通じて育まれる共感の絆こそが、災害時の助け合いにも、日常の安心にもつながります。
従来の「かわいそうだから支援する」という発想ではなく、「共感をベースに一緒に歩む仲間」としての関係づくり。これこそが、助成金の審査員にも伝えたい新しい支援モデルです。
御近助ネットワークは、単なる人のつながりではなく、“支援者予備軍”を生み出す仕組みでもあります。
共感をきっかけに誰もが「助け合う当事者」へと変わる。
その未来を、ハッピーライドは本気でデザインしているのです。