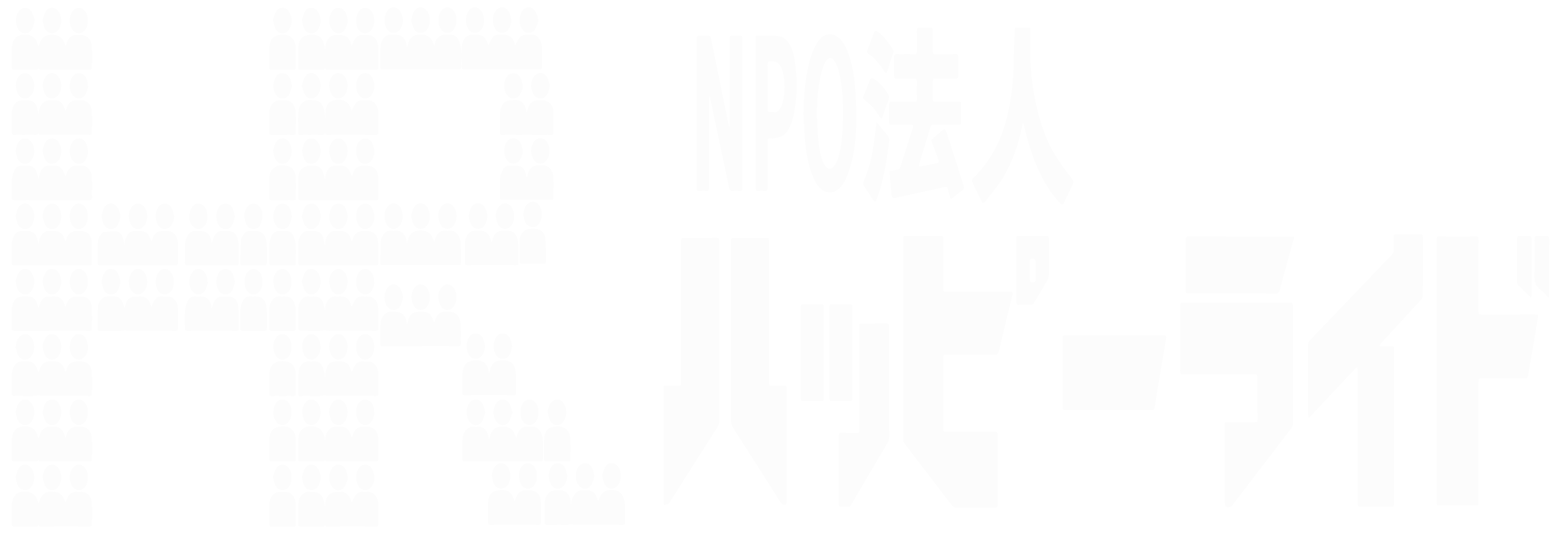目次
Toggle災害が起きたとき、「誰かの手を借りなければ何もできない」なんて言わせたくない。
でも、だからといって「一人でなんとかしろ」というのも違う。
自助と事前防災についての図を考えてみました。

視覚障がい者防災研究会は、視覚障がいのある本人やその家族が
「防災」を自分ごととして考えられるようになるための場を広げています。
そしてもう一つの軸は、「支援のあり方」を一緒に考えてくれる仲間を増やすこと。
今回は、そんな私たちの新しい活動指針とチャレンジについてご紹介します!
①「自分のこと」として考える防災
避難できる?できない?その前に「知る」
「避難できますか?」と聞かれたとき、即答できる人は案外少ない。
私たちは、まず「知識の差」が行動の差につながることに着目しています。
視覚障がい者自身が、災害時に起こるかもしれないことや、避難の選択肢の広げ方について学ぶ場をつくっています。
「避難所に行く/行かない」だけでなく、「家で備える方法」も含めて、自分に合った備え方を見つけるサポートをしています。
「できないこと」ではなく「できる形」を探す
「暗いところが苦手」「段差が見えない」「情報が入らない」──
視覚障がい者が直面する困難は、実は“工夫”で解決できることも多いのです。
私たちは、「できないこと」を起点にせず、「どうすればできるか?」を一緒に考えることを大切にしています。
支援機器の体験会や、避難所での交渉ポイントの共有など、行動につながる実践型の学びを増やしています。
②「顔の見える関係」をつくる防災
支援される側から“支える側”へ
「避難所でただ待っている存在」ではなく、「リーダーとして避難所を助ける立場」に。
視覚障がい者が“支援される側”だけでなく、“頼られる存在”にもなれるように、
防災リーダー育成のプログラムも行っています。
実際に、地域の避難所運営に携わる当事者も増えてきました。
その一歩は、「自分も何かできる」と気づくこと。私たちがそのきっかけをつくっています。
ご近所ネットワークで安心を広げる
いざというときに支えてくれるのは、制度でも、遠くの親戚でもない。
**日常のなかで顔を合わせる“近くの人”**です。
だからこそ、地域の人とゆるやかにつながる交流会や、安心して話せる小さな集まりを大事にしています。
支援する・されるという関係ではなく、「お互いさま」として声をかけ合えるつながりを育てたいのです。
③「みんなで考える」防災の仕組み
制度とつながる、声を届ける
福祉や防災の制度は、現場のリアルが届いてこそ変わっていきます。
私たちは、現場で出てきた「こうしてほしい」「ここが困ってる」という声を行政や制度担当者につなぐ役割も担っています。
たとえば、「避難所に誘導表示の点字ブロックがない」「ヘルプカードを見ても内容が分からない」など、当事者ならではの視点を提言として整理し、届けています。
防災を“まじめに”じゃなく、“おもしろく”
防災って、どうしても「真面目でお堅い」イメージがありますよね。
でも私たちは、「まじめに学ぶけど、楽しく続ける」ことを目指しています。
防災ババ抜き、暗闇体験、共感トークゲーム、安心リュックお披露目会……
いろんな工夫を凝らしながら、“参加したくなる防災”をつくっています。
これからも「おもしろくてためになる」取り組みをどんどん展開予定です!
最後に──「一緒に考える」が未来を変える
防災や避難に「正解」はありません。
でも、「一緒に考えてくれる人がいる」ことが、どれだけ心強いか。
私たち視覚障がい者防災研究会は、「できない」や「不安」を責めずに、
どうすれば「できる」につなげられるかを、一緒に考える仲間づくりを続けていきます。

次に声をかけるのは、あなたかもしれません。
まずは小さな一歩から、一緒に始めませんか?
賛助会員を募集しています
 wo
wo