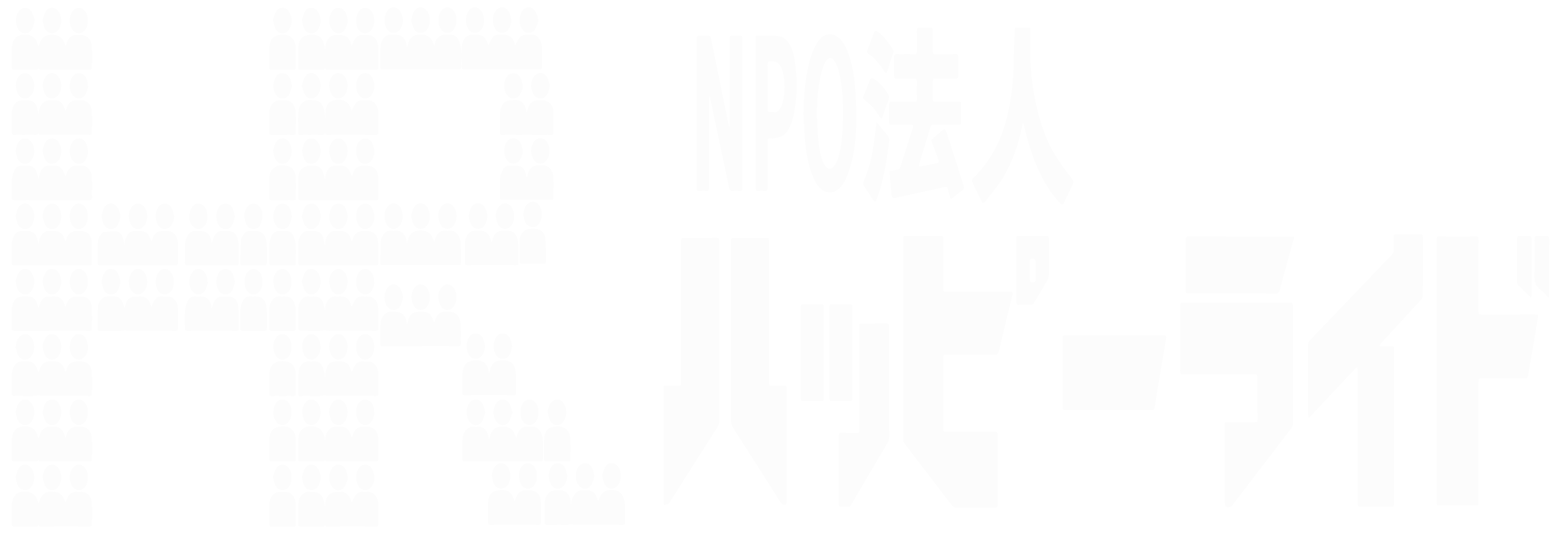🌏 共感から関係性へつなぐ防災プログラム(構想文)
🎯 目的・背景
災害時、視覚障がい者や車いすユーザー、発達障がいのある方をはじめとする「要支援者」は、避難所に行くことを諦めてしまう現実があります。その背景には、情報が届かない、支援を頼みにくい、「迷惑をかけるかもしれない」という不安や遠慮、そして過去の体験に基づく“あきらめ”が存在します。
本プログラムでは、こうした“避難のあきらめ”に光を当て、障がい特性への理解を深めると同時に、「支援の方法」ではなく「関わり方」そのものを問い直します。
🧭 プログラムの軸
「助け方」ではなく、「関わり方」を育てる。
参加者はリアルに再現された“もしも”の避難所空間の中で、要支援者の立場や心情を体感します。特に視覚障がい者の立場では、「情報が届かない怖さ」「動けない不自由さ」「伝わらない苦しさ」を体験し、そこに潜む“気づかれにくい配慮不足”を学びます。
👫 ターゲット参加者
- 視覚障がい者本人やその家族
- 車いすユーザーや発達障がいのある方
- そして「これまで深く考える機会がなかった」一般の住民(子ども・保護者・地域リーダーなど)
- 「優しい世界の住人」=何かしたい気持ちはあるが、方法がわからない人たち
🚪 プログラムのねらい
- ✅ 災害時の“誤解・すれ違い”を事前に防ぐ知識と視点を共有
- ✅ 障がい特性への理解と、その人の「背景」に気づく対話を促す
- ✅ 「配慮=特別なこと」ではなく、「関係性から生まれる行動」として捉え直す
- ✅ “頼れない人に気づく目線”と、“声をかけるきっかけ”を手に入れる
💡 具体的な体験・要素例
- 視覚障がい者の「声がかけづらい」「自分からは動けない」状態を再現
- 情報が届かない、見えない中でどう行動が変わるかを疑似体験
- 「助けなきゃ」ではなく「話しかけてみる」「様子を気にかける」という関係性のきっかけを演出
- 体験後には「どうすれば良かったか?」を語り合うリフレクション・タイム
🔁 最後に
防災の知識や技術ももちろん大切。
でも、まずは“気づく”ことから始まる防災がある。
視覚障がい者防災研究会が届けたいのは、
「共に生きのびる」ための心の準備。
【今日のひとこと】
✅ 市民主体の避難所運営は本当
📘 福岡県のガイドライン
「福岡県避難所運営マニュアル作成指針」(2025年2月改訂)には、こうあります:
避難所となる施設の管理者、自主防災組織等の地域住民、…大規模災害時に避難所の運営に関わる人々が活用できるように…整理されています city.chikushino.fukuoka.jp+9pref.fukuoka.lg.jp+9town.shime.lg.jp+9
つまり、避難者自身や地域住民による自主的な運営が前提として明記されています。